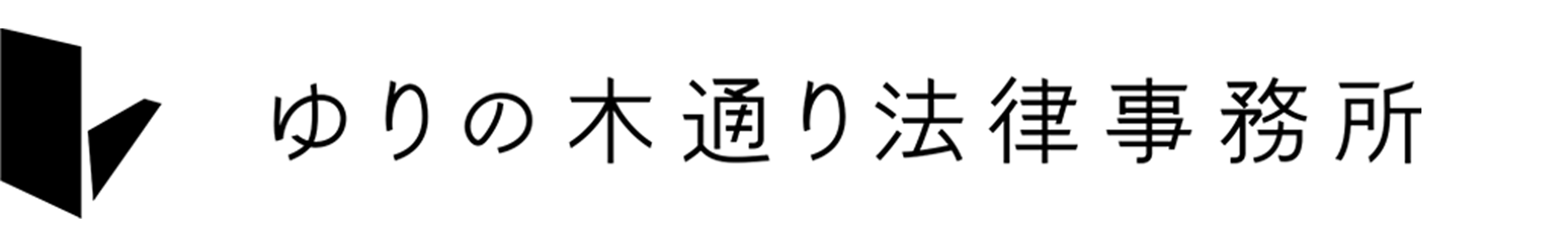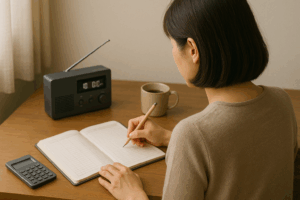離婚事由より未来を見据える重要性
はじめに
当事務所の相談者には、「どのような事実があれば離婚できるのか」、「不貞の証拠はこれで足りるのか」、「暴力の証拠が薄いのではないか」などと、離婚事由や証拠の強さにこだわる方がいらっしゃいます。そのお気持ちはとても自然ですし、決して間違いではありません。ただ、離婚事由だけに視線が固定されてしまうと、肝心なところが置き去りになってしまう場面が少なくありません。今日は、離婚に踏み出すかどうかを迷っている方に向けて、離婚への道筋を簡単に整理してみましょう。
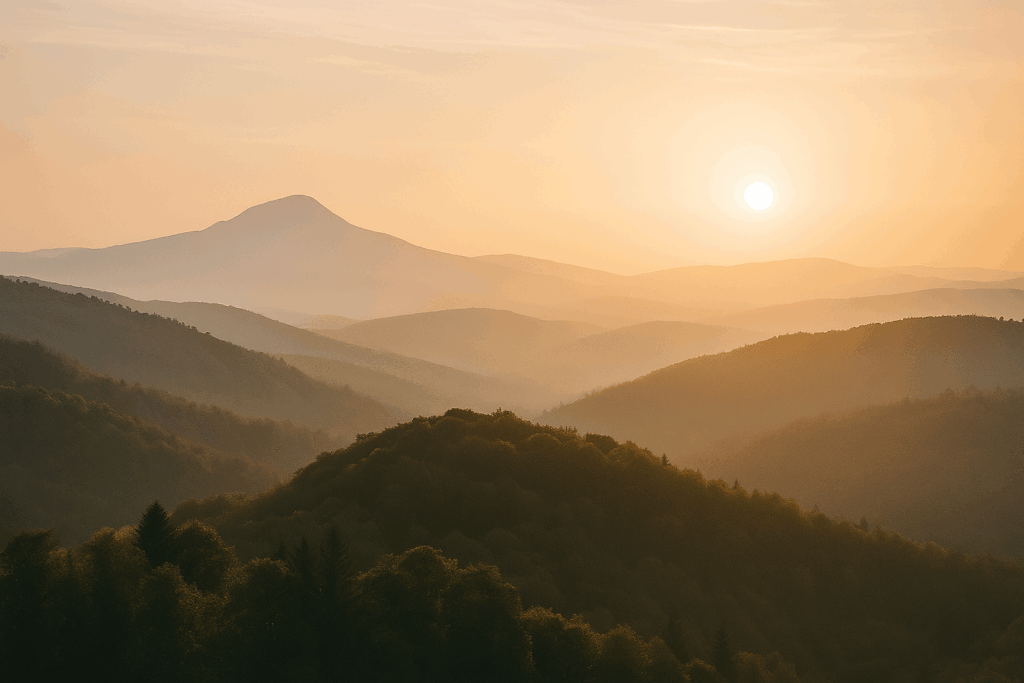
離婚には3つの道筋がある
日本での離婚には、協議離婚と調停離婚と裁判離婚の3つの道筋があります。このうち協議離婚と調停離婚は、当事者であるお二人の意思が合致すれば成立します。つまり、たとえば不貞があったかどうかといった個別の離婚事由が法律上の意味を決定づけるのではなく、将来に向けてどのような条件に合意できるかが中心になります。
親権者、養育費、面会交流、引っ越しの時期、学校や保育園の調整、連絡方法のルール、財産分与、年金分割など、日々の暮らしに直結する約束事を一つずつ形にしていくことが、協議と調停の主戦場です。
一方で、話し合いがどうしてもまとまらず訴訟に進む、いわゆる裁判離婚になった場合には、民法770条に定められた離婚事由の有無が問題になります。ただし、現在の裁判所の運用では、民法770条5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」という包括的な規定を軸に、婚姻関係が破綻しているかどうかを、すべての事情を総合的に見て判断する傾向にあります。
そのため、離婚という結果を求めるために、不貞の証拠が足りるか否かなど、個別の事由に名前をつけて当てはめることより、実際の生活が元に戻り得るのかを、時間の流れと具体的な事実から見極めるイメージです。
いま大切なのは「破綻」をどう示すかという視点
婚姻関係の破綻の有無を検討する際、中心に据えられやすいのが別居期間です。別居が一定期間続き、実質的に夫婦の共同生活が終わっているといえるのか。別居に至った経緯に無理はなかったのか。修復の努力を尽くした痕跡はあるのか。このような事実が積み重なって、婚姻関係の破綻の有無が判断されていきます。
ですから、たとえば不貞の証拠を一点豪華に追い求めるより、別居開始から今日までの生活の実像を落ち着いて描けるかどうかの方が、訴訟になったときにも説得力を持ちやすいのです。もちろん、不貞や暴力などの個別事情が意味を失うわけではありません。総合考慮の材料としては重要です。また、慰謝料を請求する場合にはかかる事実の立証が重要になります。
もっとも、こと離婚という結果を求めるためには、不貞の事実も婚姻関係の破綻という大きな枠の中で評価される、そのくらいの温度感で受け止めるのが実務的です。
協議と調停は、離婚事由にこだわりすぎない方が進む
上記のとおり、協議離婚と調停離婚は、当事者が合意すれば成立します。法律上の離婚事由は要件ではありません。むしろ、離婚事由の有無にこだわり、相手の非を並べ立てるほど話し合いは硬直し、現実的な条件整理が後回しになりがちです。
協議や調停の段階で大切なのは、これからの暮らしを具体的に回していけるかという視点です。養育費として毎月いくらの入金があれば生活が成り立つのか。子どもがどちらが養育し、非監護親との面会の曜日と時間はどうするのか。財産分与はいつの時点の残高で、算定の範囲はどこまでにするのか。自宅の住宅ローンは誰がどのように支払っていくのか。将来の揉め直しを防ぐために、公正証書や履行確保の条項をどう入れるのか。こうした合意が積み上がるほど、協議や調停は前に進みます。
裁判になったときの「見られ方」を先に知っておく
協議や調停が難航し、訴訟に進んだ場合、裁判所は770条5号を軸に、婚姻関係の破綻の有無を検討します。特に別居がどれくらい続いているか、その間の生活の実態はどうか、修復可能性は残っているか、といった夫婦関係の細かい事実の積み重ねが重要です。そのため、訴訟も視野に入れて準備するなら、過去の出来事の断片的な証拠を寄せ集めるより、時系列のノートを作って、別居の開始、家計の分離、子どもとの関わり、連絡方法の変遷、修復に向けた試みの有無などを、落ち着いて並べておく方が役に立ちます。
証拠という言葉に過剰なプレッシャーを感じる必要はありません。写真や録音だけが証拠ではなく、LINEやメールのやり取り、家計の入出金記録、学校や病院からの案内、役所や相談機関に残ったメモなど、日常にある客観的な材料で十分に全体像が描けることが少なくありません。大切なのは、作り物ではない当事者の関係性の変化が伝わることです。
子どもの暮らしを最優先に
親権者指定の判断は、どちらが悪いかという責任論ではなく、子どもの利益を最優先に考える運用になっています。離婚事由がどうであれ、子どもが安心して暮らせる環境がどちらに整っているか、きょうだいはなるべく一緒にいられるか、通学や通院は無理なく続けられるか、面会交流は現実的に実施できるか。ここでは、感情より運用可能性が重んじられます。離婚事由にこだわりすぎて、子どもの暮らしという視点が抜け落ちてしまわないよう注意してください。
財産分与は早めに全体像を
財産分与は、婚姻生活の中で一緒に形成した財産を公正に分ける考え方です。誰が有責かという点は基本的には限定的にしか影響しません。
預貯金、証券、保険、不動産、退職金の扱い、負債の共有か個別か、評価時点をいつにするか、名義がどちらかに偏っていれば移し替えの方法をどうするかなど、検討しなければいけない点は多岐に上ります。当事者間にどのような財産があるのか、同居しているうちに確認をしておく必要があります。
婚姻事由にこだわりすぎて、現実的なお金の問題を忘れないようにしましょう。
まとめ
離婚への道筋は3つ。協議と調停は、当事者の合意があれば成立しますから、離婚事由そのものは大きな意味を持ちません。裁判離婚になっても、現在の実務は770条5号の包括規定のもと、婚姻関係が破綻しているかを、すべての事情の総合考慮で検討します。総合考慮の中心には別居期間とその実態が据えられやすく、個別の離婚事由に名前をつけて当てはめること自体に、過度の重みは置かれていません。
だからこそ、最初の一歩は、離婚事由の「強さ」を測ることではなく、これからの生活をどう回すかを静かに設計することです。子どもの毎日、住まいと仕事、お金の流れ、連絡のルール。それらが実行できる形で整ってくると、協議も調停も進みやすくなり、万が一裁判になっても、破綻という全体像が自然に伝わる準備ができているはずです。
もし今、心の中に大きな波が立っているなら、まずは深呼吸をして、できるところからで構いません。これまでのこと、これからのこと、時系列のメモを少しずつ書く。毎月の入出金をわかるようにしておく。子どもの予定を書き写しておく。信頼できる人に状況を共有しておく。その小さな一歩が、未来の自分をしっかり支えてくれます。
必要であれば、あなたの事情に合わせて、弁護士が合意書の文案やチェックリストを一緒に作っていくこともできます。無理のない歩幅で進めていきましょう。