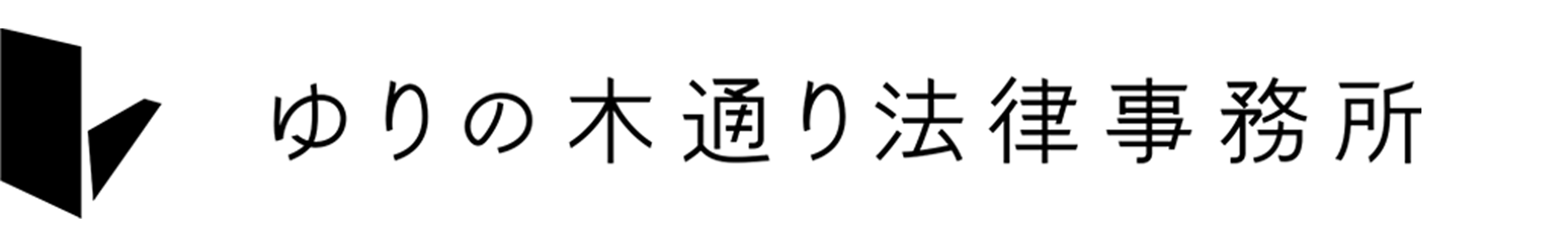【判例紹介】未成年者の心情を考慮して、直接的な面会交流ではなく、電話や手紙による間接交流が相当であると判断された事例(奈良家庭裁判所審判令和2年9月18日家庭の法と裁判39号79頁)
事案の概要
A(父)とB(母)は、平成20年に婚姻し、平成21年に長女Cが、平成23年に二女Dが生まれた。Bは、平成29年7月に二人の子を連れて別居した。平成30年2月にAがBに対して夫婦関係調整調停及び未成年者らの面会交流を求める調停を申し立てた。令和元年8月、AとBとの間で、未成年者らの親権者をBと定めて離婚が成立したが、面会交流調停は不成立となり、審判手続に移行した。
審判の内容
裁判所は、未成年者らの状況やきょうだい間の関係から、面会交流の時期、方法を定めるにあたっては、未成年者らで同じ内容の実施要領を定めるのが相当であるとした。また、期間については、長女C小学校を卒業すると生活状況や環境が大きく変わることから、令和4年3月までの実施要領を定めるのが相当であるとした。
次に、交流方法として、直接の交流については、長女Cが同居中のAの言動などを理由に直接会うことを怖がっていることに加え、Bが離婚後もAに恐怖心を抱いている姿を見て不安を感じていること、Dも直接の交流に消極的でありCと一緒では無ければ会いたくないと述べていることなどから、直ちに直接交流の実施は相当ではなく、まずは間接的な交流を重ねて未成年者らの不安と葛藤を低減していくべきであるとした。
そして、間接的な交流の方法としては、従前は電話による交流ができていたことに鑑みて、電話による音声のみの交流が相当とし、ただし頻度については未成年者らの心情に鑑みて毎月とするのは負担がかかるとして、年3回春夏冬の各長期休みに1回ずつ、一人あたり20分とした。
その他、手紙や贈物については、従前の実績を踏まえて、手紙については2か月に1回、贈物については誕生日とクリスマスについて認めるのが相当であるとした。また、Bは、上記間接的な交流を補うために、月1回未成年者らの写真を、年1回未成年者らの通知表を送付するものとした。
解説
本件は、当面の間の面会交流の方法について、未成年者らの心情を踏まえ、直接交流は相当ではないとし、間接的な面会交流の具体的な方法について詳細に検討した事例である。
面会交流について、現在の裁判所の運用としては、「父母が離婚又は別居しても、子にとって親であることに変わりがなく、非監護親からの愛情も感じられることが子の健全な成長のために重要である。…子の養育・健全な成長の面からも、一般的には、親との接触が継続することが望ましく、可能な限り家庭裁判所は親子の面会ができるように努めることが民法766条の意図するところとされている。国民の意識も、面会交流を積極的に捉えており、我が国及び海外における心理学の諸研究によると、一方の親との離別は子にとって最も否定的な感情体験の一つであり、非監護親との交流を継続することは子が精神的な健康を保ち、心理的・社会的な適応を改善するために重要であることが基本的な認識になっている」(東京家事事件研究会編『家事事件・人事訴訟事件の実務』法曹会、2015、pp191-192)との考え方を前提に、子の利益に反する事情のない限り、原則として面会交流を実施させている。
具体的な検討の過程としては、まず面会交流の実施により子の利益に反する事情があるかどうかについて、 ①子、同居親及び別居親の安全、②子の状況、③同居親及び別居親の状況、④同居親及び別居親と子の関係、⑤親同士の関係、⑥子、同居親及び別居親を取り巻く環境という6つのカテゴリーに属する事情を総合的に考慮し、子の利益を最も優先して考慮するとの観点から検討する。そして、現時点では面会交流をすることが子の利益に反する事情がある場合には、直接交流から間接交流まで、どこまでの交流を禁止する必要があるか、禁止する場合には期間を定めた禁止で足りるか、どの程度の期間とすべきか、その期間を経過した後の交流はどのような方法によるべきかを順に検討していく。そのような事情がなく、直接交流の実施が適当といえる場合には、その回数、頻度、日時、場所、方法、第三者機関の利用の有無を検討する。直接交流が適切ではないときは、間接交流を実施するのが相当か、どのような方法での間接交流を実施するのかを検討し、時期を見て間接交流から直接交流に移行するのが適当か、その場合には直接交流にどのような段階を経て至るべきかについて検討する。(東京家庭裁判所面会交流プロジェクトチーム「東京家庭裁判所における面会交流調停事件の運営方針の確認及び新たな運営モデルについて」家庭の法と裁判26号129頁参照)
本審判では、Cが同居中のAの言動に恐怖心を抱き、現在も直接交流に不安を有していること、母であるBもAに対して恐怖心を抱いている姿を見ていること、Dについても直接交流には否定的な態度を示していること、及びDはCと一緒でなければ交流は無理だと述べていることという事実関係から、直接交流の実施は相当ではないとの結論に至っている。C(小学校5年生)やD(小学校3年生)のように、自分の気持ちを明確に伝えることのできる年齢の子の場合、同人が直接交流に否定的な感情を有していることは、裁判所が重視する要素であることが分かる。
また、本審判では、間接交流について、電話、手紙、贈物の順に検討がなされており、電話による交流ついてはCDが否定的であったものの、過去に実施した際にAの対応が不適切なものではなかったことを理由に実施を認めている。ただし、その頻度は年3回と極めて限定的なものとし、CDの感情を重視していることが窺える。手紙や贈物についても、詳細に検討がされており、A及びBの立場についても配慮がされていることが分かる。
面会交流調停や審判において、面会交流を求める立場であっても、逆に求められる立場であっても、自らの意向を裁判所に伝える際には上記の判断枠組みを意識し、自分や子どもの状況を具体的に伝えていくことが重要であると改めて考えさせられた事例である。